心拍数とトレーニングの関連性や効果については。様々な所で伝えられているのでご存じの方も多くいらっしゃるかもしれません。
最近では「心拍数トレーニング」などという言葉もチラホラ見かけるようになり、ウェアラブル端末を活用してトレーニング中の心拍数を計測する方も増えてきているようですね。
ウェアラブル端末などを使用し心拍数を計測してトレーニングを行うと、トレーニング中の自分の身体の状態や消費カロリーなどの効果がリアルタイムで可視化する事が出来ます。今まで感覚でトレーニングを行ってきた人が、トレーニング効果を数値で判断出来る所に評価が高まり利用者が増えてきているのだと思います。
ここでは心拍数とトレーニングの関係について紹介して行きたいと思います
目次
トレーニングにおける心拍数の考え方
運動をより効果的に行うための方法として「心拍数」を管理するトレーニングがあります
最近ではフロリダに本部があり全世界に800店出店しているオレンジセオリーや、国内では暗闇ボクシングフィットネスのb-monsterなどが心拍数を図りトレーニング効果を計測するサービスを打ち出してきています。
何故、心拍数を計測するとトレーニングを効率的に行うことが出来るようになるのでしょうか?
その理由は今までの「キツい」「ラク」と言った感覚から「心拍数」という具体的な数値でトレーニング内容を把握する事が出来るため、そのトレーニングの目標を明確にする事が出来るのです。
走ったりキツい階段や坂道を登ると、息が切れ心臓がバクバクする事があると思います。これは心拍数が上がったからに他なりません。
そして心拍数が上がるのは身体が酸素を必要としているからで、運動強度が高ければ高いほど必要な酸素も増えるので心拍数も上がりやすくなります
普段の生活でも階段を上ったりキツいと感じる方が心臓もバクバクしますよね?
そしてこの心拍数のコントロールをする事で「脂肪燃焼」や「持久力向上」、そして「筋力向上」「瞬発力向上」、さらには「健康増進」など、今行っているトレーニングにどんな効果があるか一目で把握する事が出来るようになります
心拍数のゾーン
心拍数は数値(BPM)により、身体に与える影響も異なってきます。
一般的には大きく分けて3つのゾーンに分けられます
脂肪燃焼ゾーン
強度としては低~中程度の運動ゾーンで、脂肪は燃え始めているものの、燃焼速度は低い状態です
健康維持などを目的とした軽めの運動や、身体に大きな負荷が掛からないような「ウォーキング」などがこのゾーンになります。
有酸素運動ゾーン
強度としては中~高の運動ゾーンで、20分以上続けると溜まった体脂肪が直接エネルギー消費される状態です
酸素を使い筋肉を動かすエネルギーである脂肪を燃焼させることから有酸素運動といいます。脂肪を消費するため、ダイエットなどはこのゾーンを目標とします。体脂肪の減少などに効果が期待できます。代表的なトレーニングとしては「水泳」や「ジョギング」などが上げられます。
無酸素運動ゾーン
高強度の運動ゾーンで、短時間に行う強度の高い運動や、瞬発的な動きで筋肉内の糖質が使われて筋肉が鍛えられ、基礎代謝がアップする状態です
筋肉を動かすためのエネルギーを、酸素を使ないため無酸素運動と呼ばれています。エネルギーの発生に酸素を必要とせず、糖をエネルギー源として利用します。代表的なトレーニングとしては「短距離ダッシュ」や「筋力トレーニング」などの短時間、なおかつ運動強度の高いものがあてはまります。
このように心拍数のゾーンにより運動効果が異なるため、最近では有酸素運動ゾーンと無酸素運動ゾーンを効率よく取り込め、短時間でその効果を発揮する「HIIT(高強度インターバルトレーニング)」が注目されているのだと思います。
目標心拍数の算出方法
目標心拍数はそれぞれの最大心拍数からどれくらいの強度で運動しているかで把握する事が出来ます。
この目標心拍数を求めるためには、自身の最大心拍数を知る事が必要です
最大心拍数とは
簡単に説明をすると、最大心拍数とはトレーニング中の1分間に心臓がドクンと動く最大の数を意味します。最大心拍数は年齢やその人の運動頻度などよっても異なります。
ここでは最大心拍数の求め方を説明していきます。最大心拍数はいくつかの方法で算出することができます。
- 専門機関で計測
- フィールドテストを実施して計測
- 平地で15分間ウォームアップします。ゆっくりといつものトレーニングペースまで上げていきます
- 上るのに2分間以上かかる坂または階段を選びます。坂/階段を20分間走って上ります。その際に、最大のペースを維持します。20分後、坂/階段の下に戻ります。
- 3キロを休まずに進めるだけのペースで坂/階段を再度駆け上がります。最大心拍数を記録します。最大心拍数は記録した心拍数よりもおよそ10拍高くなります。
- 心拍数が1分間に30-40拍下がるように、坂を下ります。
- 1分間だけ走れるだけのペースを保ちながら坂/階段を再度上がります。坂/階段の中盤まで行けるようにがんばります。最大心拍数を記録します。これにより正確な値に近い最大心拍数を得ることができます。トレーニングゾーンを設定する際に、この最大心拍数をお使いください。
- 最低10分、必ずクールダウンしてください。
- 計算式から算出
これは中々ハードルが高いですね。そもそも専門機関はどういった所が有るのかもよく分からないかとおもいます。
一般的には医療機関などでも計測を行っている所もあるそうですが、なかにはこんな団体もあり予約をすれば計測して貰えるそうです。
公益法人 東京都スポーツ文化事業団
ここではやり方を紹介してみようとおもいます。
これはPOLAR(ポラール)という運動効果を計測する機器を開発/販売している専門企業が提供していた内容です。
普段からハードなトレーニングなどを行っていれば、ご自分で最大心拍数を計測するためのテストを安全に受けることができます。ただし安全のためテスト中はトレーニングパートナーが付き添うことをお勧めします。また、テストを受けることができる健康状態であるか心配な方は医師にご相談ください。
- 簡単なテストの例を紹介します
・・・これはかなり大変そうですね。
もっと簡単に行うための方法として、ジョギングなどである程度身体を温めてから、1500Mを全力でダッシュしその際の心拍数をはかるというやり方もあるそうです。
最大心拍数の求め方としては「カルボーネン法」という理論があり、「220-年齢」という至って簡単な計算式になります。実はこの数値には科学的根拠が乏しく、個人差が激しいそうで「220-年齢」を最大心拍数とする場合は参考程度の数値とした方がよいかもしれません。
また、最近では最大心拍数を求める計算式で「207-(年齢×0.7)」が使われる事もあるそうで、こちらの方が精度が高いという専門家もいるそうですね。年齢が低いとカルボーネン法の計算式とほぼ数値は変わらないのですが、年齢が高くなると変わってくるようですので、こちらの計算式も試してみて下さい。
最大心拍数から算出する運動強度
ここからは更に細かく心拍数のゾーンを分けてみたいと思います。ここでもPOLAR(ポラール)などのウェアラブル端末などによくある5段階に分けたいと思います
| 心拍数ゾーン | 強度、最大心拍数からの%(bpm) | トレーニング効果 |
|---|---|---|
非常にハード |
90~100%171~190bpm | 効果 → 最高のパフォーマンスとスピードを開発 トレーニング強度 → 呼吸および筋肉への大きな疲労 おすすめ → 健康で丈夫な方や運動トレーニング向け |
ハード |
80~90%152~172bpm | 効果 → 最高のパフォーマンス能力を改善 トレーニング強度 → 筋肉への疲労感および激しい呼吸。 おすすめ → 短時間の運動を行う方向け |
中 |
70~80%133~152bpm | 効果 → 有酸素フィットネス度の向上 トレーニング強度 → 軽い筋肉の緊張、負荷の軽い呼吸、適度な発汗 おすすめ → 適度に長時間の運動を行う方向け |
軽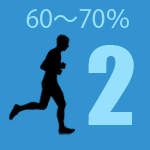 |
60~70%114~133bpm | 効果 → 基本的な基礎耐性と脂肪燃焼を向上 トレーニング強度 → 快適、負荷の軽い呼吸、筋肉への軽い負荷、軽い発汗 おすすめ → 短時間の運動を長期に渡って頻繁に行う方向け |
低 |
50~60%104~114bpm | 効果 → 全体の健康を改善しリカバリーを支援 トレーニング強度 → 呼吸および筋肉への軽い負荷 おすすめ → 体重管理と効果的なリカバリー |
心拍数トレーニングの注意点
心拍数把握する事でどのようなトレーニングが行えているか、また、自分の目的を達成する為にはどんなトレーニングが必要かが、感覚では無く視覚的に数値で判断することが出来るのはとても効率的で素晴らしい反面、コントロールを誤ると心臓に過度な負荷をかけてしまう事も想定出来るので注意が必要です。
数値を追いかけすぎ自分の限界以上に身体を追い込んでしまい、心臓に大きな負荷が掛かると言うことが想定出来ます
高負荷のトレーニングを長時間続けた結果、最悪の場合は心停止・・・などという話も想定出来なくありません。
その日の体調を十分に把握し、今まで行ってきたトレーニングと数値と明らかに高い場合などは、一度運動をやめ脈が落ち着くまで心肺を休ませることを行って下さい
心拍数とトレーニングの関係についてのまとめ
このように心拍数を図ることで、今行っているトレーニングがもたらす効果を把握することが出来るようになるのです。
また心拍数により、その日の体調や調子なども把握する事が出来るようになります。
ぜひウェアラブル端末などを使用し、トレーニングに心拍数管理を取り入れてみてはいかがでしょうか。




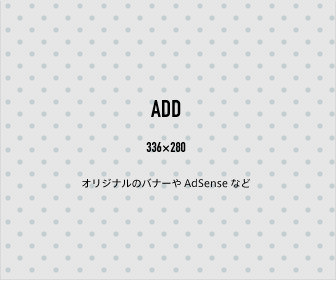


コメントを残す